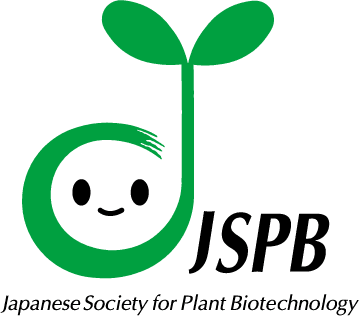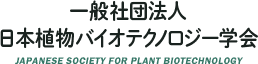講演発表の特許手続に用いる証明書の作成について(2004年7月21日)
本会は特許法第30条第1項の規定による「特許庁長官が指定する学術団体」に指定されておりますので、本大会・シンポジウムで講演発表をし、1)その発表した日より6ヶ月以内に(講演要旨発行日より起算)、その発表者が実用新案または特許について『特許法第30条第一項の適用を受けようとする旨を記載した書面』を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、2)さらにその発明、考案が『本会で発表されたものであることを証明する学会発行の「証明書」』を出願の日より30日以内に特許庁長官に提出するときは、その発明、考案は新規性を失わないと認められることになっています。なお、これらは日本国内及び米国においては有効ですが、EUでは認められません。
特許庁のホームページは [ https://www.jpo.go.jp/index.html ] です。
証明書の作成は下記のような手順で行います。質問等がありましたら、学会事務局にお問い合わせください。
大会・シンポジウムの講演要旨に書かれていることのみを特許の対象にする場合には、下記の1-aを2通作成して学会事務局に返信用封筒を同封の上、送付するだけで手続は完了します。この場合には学会事務局に事前に連絡する必要はありません。一方、要旨に書かれていること以外の発表内容を特許の対象とする発表者は、下記の全ての指示に従ってください。
- 書類は、下記の2種が必要
a >> 「証明書」2通 ひな型ファイル
学会長印とその割り印を押す。後日、1通を学会事務局で保管する。
b >> 「確認書」1通 ひな型ファイル
座長および大会委員長の印鑑を押す。「証明書」に学会長印を捺印するための内部書類。後日、学会事務局で保管する。 - 発表者は、大会1週間前までに上記「証明書」と「確認書」を学会事務局に電子メイルの添付ファイルあるいはファックスで送付するとともに、大会当日、大会本部に、返信用封筒とともに、「証明書」2通を持参する。
- 学会事務局は、大会準備委員会(以下、大会本部)に特許講演が予定されていることを連絡する。大会本部は、当該講演の座長に対し、特許証明のある発表が予定されていること、印鑑を学会場へ持参することを依頼する。予め書類の授受の日時・場所等の打ち合わせをしておくことが望ましい。
- 学会事務局は、学会当日までに大会本部へ「証明書」2通と「確認書」1通(写し)を届ける。大会本部は、講演当日の当該講演の前までに、当該講演の座長に「確認書」と「証明書」を渡す。
- 講演発表の間、座長は「証明書」(写し)の講演発表の内容との照合・確認を行う。講演終了後、座長交代以後のできるだけ早期に、座長は「確認書」に署名・捺印し、大会委員長に提出する。
- 大会委員長は「確認書」の座長による署名・捺印を確認の上、「確認書」の大会委員長の項に捺印し、学会事務局に届ける。学会事務局は、「確認書」を確認の上、「証明書」2通に学会長印を押す。「証明書」1通を発表者へ返却する。「確認書」と「証明書」1通は学会事務局にて保管する。
(注1) 書類の授受は、書留郵便または宅配便等の受け取りが確認できる方法で送付するか、または確実に手渡すようにする。
(注2) 以上は大会前1週間以前に書類が準備された場合の説明である。大会1週間以内になってから特許取得の必要性が生じた場合、「証明書」の内容に訂正・変更が生じた場合、講演後の6ヶ月の間に講演要旨のみを対象とした申請を行う等の場合には、柔軟な対応を行うものとする。学会事務局まで連絡・相談する。