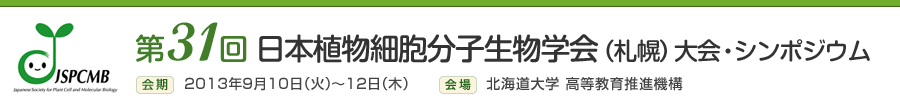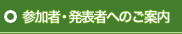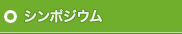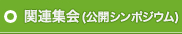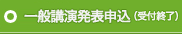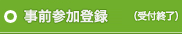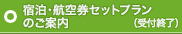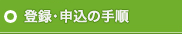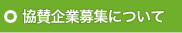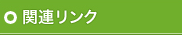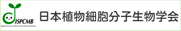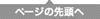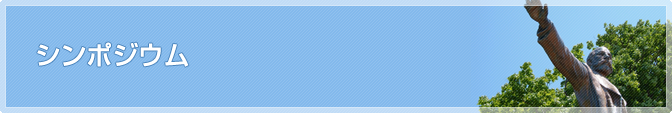
大会3日目、9月12日(木)に以下のように5件のシンポジウム・集会を予定しています。
シンポジウム1 9月12日(木) 9:00〜12:00 A会場
【学会本部企画】 産官学連携を活用した植物バイオ事業の推進
オーガナイザー:本学会幹事会・産官学連携WG
原 康弘(トヨタ自動車)、岡澤 敦司(大阪府立大)、
梅原 三貴久(東洋大)、小泉 望(大阪府立大)
本学会は、多岐にわたる専門分野の会員を擁し、また大会参加者の1/4が民間企業に所属するユニークな特徴を有することから、分野や業種を超えた学際的コミュニティとして、食糧、健康、環境、エネルギーといった多面的アプローチを必要とする諸問題に解決策を発信できる立場にある。本シンポジウムでは、産官学連携による多面的アプローチにより、製品やサービス開発に取り組んだ事例を紹介し、効果的な連携のための工夫点や成功要因を考察する。
- 「遺伝子組換え植物での医薬原材料生産実用化研究の課題と展望」
- 松村 健(産総研生物プロセス)
- 「オールジャパン体制によるサポニン代謝工学研究とその展望」
- 村中 俊哉(大阪大)
- 「多様なシーズの融合から生まれた遺伝子組換え植物 その実用化と発展性」
- 寺川 輝彦(北興化学工業開発研)
- 「産学連携による植物由来高機能バイオポリマー(トチュウエラストマー)の事業化」
- 中澤 慶久(大阪大/日立造船技術開発本部)
- 「リバネスが創る産学連携の新しい形」
- 丸 幸弘(リバネス/ユーグレナ)
シンポジウム2 9月12日(木) 13:00〜17:15 B会場
「アグロバクテリウムによる単子葉形質転換法 --- 20年の歩みと今後の展開」
オーガナイザー:小鞠 敏彦(日本たばこ産業)
土岐 精一(農業生物資源研)
アグロバクテリウム利用の遺伝子導入法は、現在では、広範な植物において用いられる研究手法である。しかし、約20年前までは、単子葉植物には利用できないと考えられていた。この問題の克服、アグロバクテリウムと植物細胞の関わり、基礎研究の重要性、遺伝子導入手法の改良・利用の推進、実用的な作物品種開発、ゲノム研究やジーンターゲティングへの利用など、さまざまな話題を取り上げ、研究の進展と今後の課題を議論する。
- 「アグロバクテリウムによる単子葉形質転換はなぜ困難だったのか?」
- 小鞠 敏彦(日本たばこ産業)
- 「This importance of basic research for next generation crops: TALENs, non-coding RNAs, and nanotechnology」
- Kan Wang(Iowa State Univ.)
- 「Transformation of maize for commercial trait development: successes and perspectives」
- Qiudeng Que(Syngenta)
- 「主要穀物の形質転換技術の進歩」
- 樋江井 祐弘(日本たばこ産業)
- 「アグロバクテリウムT-DNAによる植物器官不全と細胞増殖異常の仕組み」
- 町田 泰則(名古屋大)
- 「Application of gene transfer methods for functional genomics in rice」
- Gynheung An(Kyung Hee Univ.)
- 「イネの標的遺伝子改変技術の展開」
- 土岐 精一(農業生物資源研)
シンポジウム3 9月12日(木) 9:30〜12:00,13:30〜16:00 C会場
「バイオインフォマティクス講習会」
オーガナイザー:矢野 健太郎(明治大)
草野 都(環境資源科学研究セ)
高速シーケンサー、ゲノム解読とアノテーション、トランスクリプトーム、メタボロームなどの大規模解析手法、および、それらのデータベースやツールについて紹介する。
- 「高速シークエンサ由来配列のアーカイブデータベースと解析パイプライン」
- 神沼 英里(遺伝学研)
- 「イネ科植物のデータベース:レファレンスから品種間比較へ」
- 伊藤 剛(農業生物資源研)
- 「大規模オミックス情報に基づく遺伝子探索手法」
- 矢野 健太郎(明治大)
- 「質量分析計を用いた代謝物プロファイリングパイプラインと化合物1ピークの同定・アノテーションの定義付け」
- 草野 都(理研 環境資源科学研究セ)
- 「ゲノムと量的形質の関連を探る:Rを用いたデータ解析」
- 岩田 洋佳(東京大)
- 「ゲノム情報に基づく植物データベースの統合」
- 市原 寿子(かずさDNA研)
- 「RでQTL解析 大量データへの対応」
- 清水 顕史(滋賀県立大)
- 「マススペクトルのデータベースを使いこなす」
- 有田 正規(東京大)
シンポジウム4 9月12日(木) 9:30〜12:00 D会場
「植物超低温保存の歴史と最新事情」
オーガナイザー:松本 敏一(島根大)
新野 孝男(筑波大)
前半は「日本における植物超低温保存の歴史」というテーマでこの 分野のパイオニアである北大の故酒井昭教授の思い出話も交えなが らその歴史と変遷および新しく開発された手法について、後半は 「植物超低温保存の現場への応用」というテーマで5名の研究者に 話題提供をしてもらい、植物超低温保存技術による遺伝資源保存の 将来性等、自由な話題で意見交換をする。
- 「日本における植物超低温保存の歴史」
- 新野 孝男(筑波大)
- 「植物超低温保存法の変遷」
- 松本 敏一(島根大)
- 「新しい超低温保存法「プレート法」の開発」
- 山本 伸一(農業生物資源研)
- 「植物超低温保存技術の農業現場への応用」
- 甲村 浩之(県立広島大)
- 「ガラス化法(PVS2法)の長期保存事業への展開〜ジャガイモ〜」
- 平井 泰(北海道立中央農試)
- 「植物超低温保存技術のジーンバンク事業への展開」
- 福井 邦明(農業生物資源研)
- 「基生研におけるバイオバックアッププロジェクトと保存研究の未来」
- 田中 大介(基生研)
シンポジウム5 9月12日(木) 13:00〜16:00 D会場
「タンパク質解析技術を多様な植物研究に生かすには〜タンパク質解析の現在と今後の展開」
オーガナイザー:柳川 由紀(理研 環境資源科学研究セ)
佐藤 長緒(北海道大)
モデル植物にとどまらず、作物や園芸植物など多様な植物種を対象にした研究を行う上で、タンパク質解析技術をいかに利用するか、について議論する。本シンポジウムでは、利用可能な技術やツールについて最新の研究成果と合わせて紹介する。また、タンパク質解析技術をこれからの植物研究へ生かすためには、今後どのような展開が考えられるか、についても議論したい。
- 「プロテオーム解析技術の植物研究への利用」
- 南條洋平(農研機構 作物研究所)
- 「植物のタンパク質相互作用解析を利用した生理機能解析」
- 佐藤長緒(北海道大)
- 「植物における一過的タンパク質発現系とその利用」
- 三浦謙治(筑波大)
- 「コムギ無細胞翻訳系を基盤とした植物タンパク質ライブラリーの構築と生化学的機能解析」
- 根本圭一郎(愛媛大)
- 「シロイヌナズナF-Boxタンパク質の網羅的解析と植物の機能解析で利用可能なツール紹介」
- 柳川由紀(理研 植物資源科学研究セ)
- 「植物由来タンパク質分解酵素〜研究の歴史と展望〜」
- 有馬一成(鹿児島大)